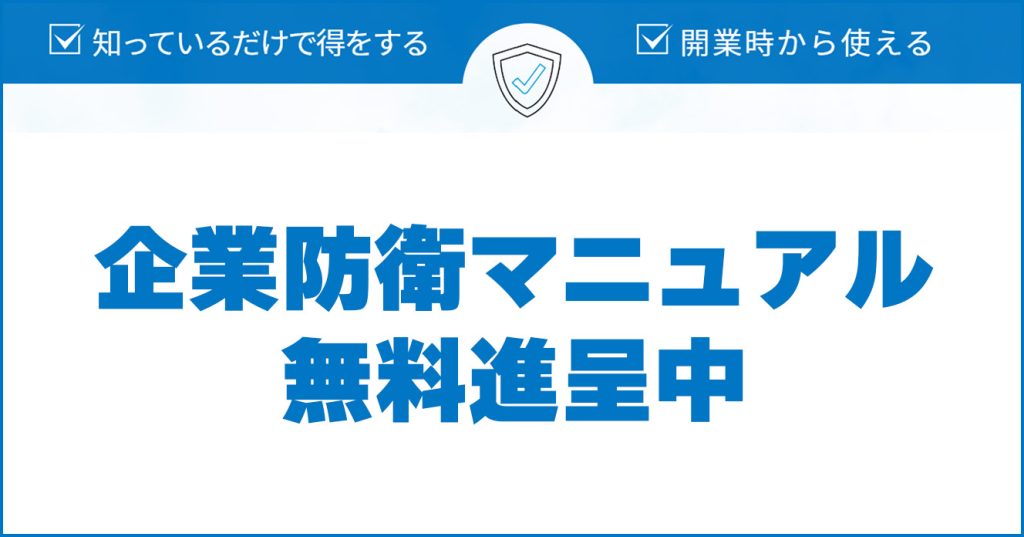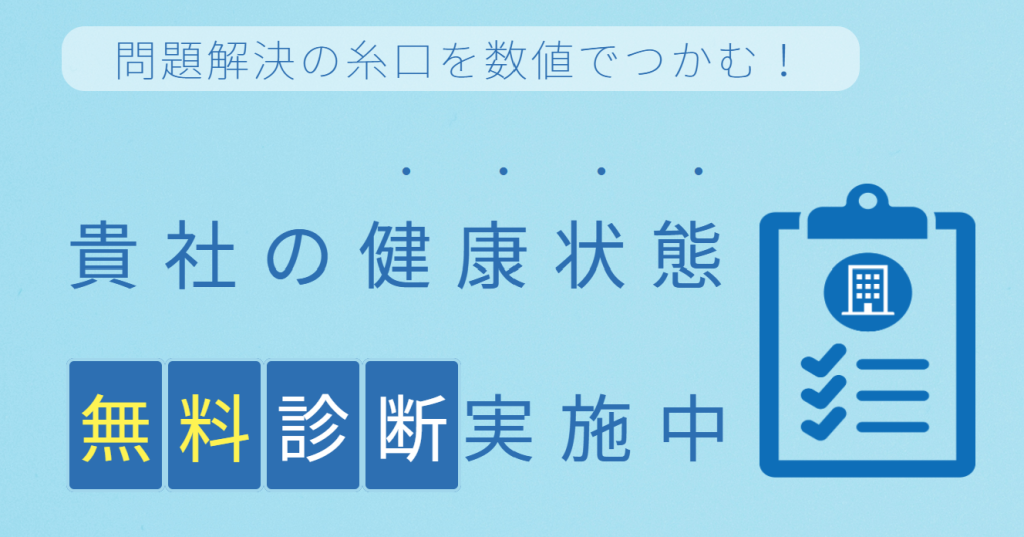今回は、弊社オリジナルの連載特集【新株予約権、ストックオプションの実務】第2回目をお届けいたします。
新株予約権評価、ストックオプション評価
ここでは、新株予約権を導入することによるメリットやデメリットを考察します。
新株予約権の利用が想定される主な場面としては、資金調達、役員や従業員へのインセンティブ、敵対的企業買収に対する防衛策の、大きく3つが挙げられます。
1.資金調達
新株予約権で資金調達?ちょっとピンときませんかね?
新株予約権が時価で発行される場合、予約権を付与された人から予約権の対価が振り込まれることになるため、ボリュームは大きくないですが、それだけで資金調達となります。
ただ、もちろんその後の株式取得によってはじめて多額の調達が可能になるため、新株予約権の発行だけが資金調達の手段となることは想定されていません。ここでいう資金調達とは、株式発行による増資もセットとして考えます。
なお、これは次回以降お話しする内容ですが、単なる第三者割当増資に比べ、新株予約権を利用した増資(新株予約権付与⇒その後予約権行使により株式の払い込みを行う)の方が機動的に資金調達が行える場合が少なくありません。ここでは、そのような事情から、新株予約権による資金調達を株式発行による増資と同義として記述しています。
企業が資金調達を行う際の手段には、銀行等の金融機関からの借入、社債の発行、株式等の発行による増資の、主に3つの手段が使われます。このうち、金融機関からの借入及び社債の発行は、金融機関等の承諾が得られれば、機動的な資金調達が可能となるものの、負債の増加により自己資本比率の悪化を招くとともに、支払利息の増加により財務状況が悪化する可能性があります。
一方、株式等の発行による増資は自己資本を増加させることから、自己資本比率の悪化を招かず、企業の財務状況の改善につながります。企業の資金調達手段が間接金融から直接金融へとシフトしつつある中で、かつてと比べると、株式発行による増資は、一般的な手段となっています。
しかしながら、増資を行う際は、増資の割当先をどのように決めるのかが課題となります。割当を既存株主に平等に行う場合、既存株主の権利は守られますが、既存株主の引受能力が無限ではない以上、資金調達の規模も限られたものとなります。
一方、既存株主以外の第三者を割当先とすれば、新たな資金調達先を確保することが可能となり、資金調達の規模を拡大させることが可能ですが、一株当たりの価値が希薄化するため、既存株主の議決権比率が低下するとともに、配当が減少し、株価の下落を招きかねないことになります。
2.役員や従業員へのインセンティブ
企業が役員及び従業員に対して支払う報酬は、通常、金銭により支払われます。役員に対しては、業績に連動した役員報酬体系がとられている企業も存在しますが、業績連動の指標を客観的に決定するのは難しく、企業価値の向上に貢献するインセンティブを与えづらい状況にあります。
また、従業員に対する給与についても、個人の成績や能力に応じた査定により、ある程度の差がつけられ、また、企業の業績によりベースアップや賞与の額が変動するのが一般的ですが、企業価値の向上に伴う利益を従業員に直接与えることは、困難が伴います。
上記を解決するインセンティブプランとして、ストックオプション制度が多くの企業で導入されています。株式報酬型ストックオプションは、新株予約権を報酬として役員及び従業員に付与するものであり、企業価値の向上により、株価が上昇すれば役員及び従業員の報酬の増加につながります。
このため、役員及び従業員が企業価値の向上のためにより積極的に業務に励むインセンティブを与えることが可能になります。
しかしながら、株価はその企業の企業価値を常に客観的に示しているとは限らず、市場全体の動向や一時的な投機的取引等により変動するため、役員及び従業員が企業価値の向上のために業務に励んだとしても、必ずしも株価に反映されない場合もあります。
なお一般論として、長期的には、株価は企業価値を反映するような価格帯に収束することが予想されることから、長期的な視点で考えると、ストック・オプションによるメリットが企業と役員及び従業員の双方に生じることが期待されます。
3.敵対的企業買収に対する防衛策
企業活動のグローバル化等に伴い、企業間の競争が激化することで、敵対的企業買収(TOB)が行われる可能性が、以前より高まっています。経営資源の不足等により、本来の価値を発揮していない企業に対して敵対的企業買収が行われた場合は、経営陣の刷新や外部からの経営資源の投入により、企業価値の向上につながる可能性があるため、敵対的企業買収が必ずしも企業にとってマイナスとは限りません。
しかしながら、敵対的企業買収においては、買収した株式の高値での買取を要求するグリーンメイラーが存在するケースや、企業買収後に子会社や資産を売却し、利益を上げようとする解体型企業買収が行われるケースがあり、必ずしも、敵対的企業買収が企業価値の向上につながらないケースがあります。
企業価値の向上にマイナスとなる敵対的企業買収を防ぐため、敵対的買収が行われようとしており、それが企業価値の向上にマイナスとなることが想定される場合、新株予約権を企業に友好的な株主等に発行することで、敵対的買収を阻止するスキームを設定する企業が、近年増加しています。
このようなスキームを実際に発動することは、既存株主の権利を害する可能性もあるため、スキームの設定時に、予め株主総会において株主の決議を得る必要があります。また、スキームが、既存の経営陣により恣意的に選択及び濫用されることを防ぐため、企業価値の向上に寄与するか否かを判定する仕組みを作る必要があります。このため、監査役や第三者による独立委員会を設置し、その委員会が、スキームの発動の可否を判定するのが一般的です。
4.今回のまとめ
新株予約権は株式に転換できるという特性を活かした使い方が可能です。しかしながら、利用にあたっては、メリットともにデメリットも存在するため、他企業の先行事例も含めて、その必要性を慎重に検討していただければと思います。
では、今回はこの辺で失礼いたします。お読みいただきありがとうございました。
新株予約権・ストックオプション連載
第2回 新株予約権を導入する意義(メリット・デメリット)(今回)
第5回 ストックオプションに関する解説
第6回 新株予約権の税務上の留意点
第7回 新株予約権の会計処理
第8回 新株予約権の評価方法
◆関連事務所提供サービス◆
【オリジナルレポート】






新株予約権評価、ストックオプション評価